認可保育所・認定こども園等利用案内
未就学のお子さん(以下、児童)が保育所等をご利用するための基本的な流れは下記の通りです。
1.希望園や利用形態を決める
認可保育所・認定こども園・幼稚園とは?
希望の条件(預ける理由、預ける時間等)によって、様々な選択肢があります。
そこでどういった施設があるのか、施設ごとにどういった利用形態があるのかについてご紹介します。
認可保育所
保護者の就労等の理由で保育を必要とする児童を、保護者の下から通わせて保育を行う児童福祉施設です。利用するためには、「保育を必要とする事由」が必要になります。
市内認可保育所一覧は下記リンク先をご覧ください。
認定こども園
上記の認可保育所の機能に加え、小学校以降の教育の基礎を培うため、満3歳以上の児童の教育を行う幼稚園の機能を併せ持ちます。
幼稚園部分は、「保育を必要とする事由」のない児童も利用ができるので、保護者の就労状況が変化した場合でも、通いなれた園を継続して利用ができます。各区分の定員等の都合により継続できない場合もありますのでご注意ください。
よって認定こども園では、満3歳以上の児童について、同じ園で同じ学年でも利用形態(認定区分)の異なる方が混在します。
市内認定こども園一覧は下記リンク先をご覧ください。
幼稚園
小学校以降の教育の基礎を培うため、満3歳以上の児童に対し教育を行う学校です。
保護者の就労等の有無に関わらず利用できます。
※宇佐市内には現在、幼稚園はありません。
気になる施設をみつけたら、施設の見学をお願いします
施設の雰囲気や保育の方針等は園によって様々です。
施設の見学については随時受付をしております。施設に直接ご連絡をしていただき、日程の調整を行ってください。
!ご注意!
近年、見学をされずに入所をして、ご家庭との保育方針との違いなどからトラブルになるケースがあります。必ず事前の見学を行ってから希望施設を決めていただくようにお願いします。
1号認定(教育標準時間認定)と2・3号認定(保育認定)について
施設に入所するためには、利用形態に応じて利用する児童が認定を受ける必要があります。
そこで、どういった認定(利用形態)があるのか、認定ごとにどの施設がご利用できるのかをご紹介します。
1号認定(教育標準時間認定)
幼稚園や認定こども園の幼稚園部分を利用するために必要な認定です。
宇佐市では満3歳になった翌月からであればどなたでも認定が可能です。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
2・3号認定(保育認定)
認可保育所や認定こども園の保育所部分を利用するために必要な認定です。
保護者(父、母等)のいずれの方も、家庭で保育できない「保育を必要とする事由」に該当する児童が認定を受けることができます。
就学前の児童は、年齢を問わずに認定することができますが、生後間もない(首が据わっていない)乳児は施設で預かることができません。
| 認定区分 | 対象年齢 | 保育を必要 とする事由 |
預けられる 時間(目安) |
利用施設 | 利用手続き の場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号認定 (教育標準時間認定) |
満3歳以上 | 不要 | 5~6時間 | 認定こども園 | ご希望の各園 |
| 2号認定 (保育認定) |
要 | 8~11時間 | 認可保育所 認定こども園 |
市役所及び 各支所 |
|
| 3号認定 (保育認定) |
満3歳未満 |
保育必要量について
保育認定では、保育必要量の認定も行います。
保育必要量は、就労時間により「保育標準時間(一日最長11時間)」と「保育短時間(一日最長8時間)」に分かれています。それぞれの認定によって一日当たりの利用時間の上限が変わります(延長保育を除く)。
!注意!
求職活動での認定の場合、就職後に保育必要量を再算定します。
保育標準時間の要件を満たす場合でも、希望により保育短時間の認定を受けることができます。
就労時間が月120時間未満の「保育短時間認定」の児童については、通勤時間の加算等により「保育標準時間認定」を受けることができる場合があります。
保育を必要とする事由について
| 事由 | 該当する状況 (保育短時間認定の要件) |
保育標準時間認定 の要件 |
認定期間 |
|---|---|---|---|
| 就労 | 月60時間以上の就労をしている場合 | 月120時間以上の就労等 | 就労している期間 |
| 妊娠 ・ 出産 |
近く出産を控えている、または産後間もない場合 | 出産予定日の前後約2カ月 | |
| 疾病 ・ 障がい |
入院中や安静を要する等常時保育ができない、または月60時間以上の通院の場合 | 入院中や安静を要する等常時保育ができない、または月120時間以上の通院 | 診断を受けている期間 |
| 介護 ・ 看護 |
同居の親族等を常時介護・看護している場合 | 月120時間以上の介護・看護 | 介護・看護が必要な期間 |
| 求職 活動 |
求職活動(起業準備を含む)を行っている場合 | 求職活動開始から90日が経過する日が属する月末 | |
| 災害 復旧 |
風水害、地震などの災害復旧に当たっている場合 | 復旧に当たっている期間 | |
| 就学 | 専門学校又は職業訓練校等に通学している場合 | 月120時間以上の就学 | 卒業までの期間 |
| 育児 休業 |
育児休業取得前に、既に児童が入所しており、その児童以外を対象とする育児休業を取得する際に継続利用が必要と認められる場合 | 休業前の就労状況に準ずる | 育児休業取得対象児童の出産から2年以内の保護者が復帰するまでの期間* |
| その他 | 保育が必要と市が認める場合 | 保育の必要量を調査の上決定 | 保育が必要と市が認める期間 |
*復帰後も同じ施設を利用する場合に限る
認定期間について
認定の始期は原則として月の初日、期限は月の末日です。
施設利用に関しても、入所する場合は月の初日、退所する場合は月の末日になります。
1号認定について、認定期限は卒園までとなります。入所期限は年度ごとになりますが、年に一度現況届を提出することで翌年度も継続利用することができます。
2・3号認定について、認定期間の満了(例:求職活動の期限切れ等)や状況の変化(例:仕事を辞めた後次の仕事につかない状態が続く等)により途中で認定できなくなった場合は保育認定での継続利用はできません。
3号認定は、満3歳になる日の前日から自動的に2号認定に切り替わります。
その他
一時預かり(一般型)事業
理由によって月5回または14回を上限に、入所ではなく一時的に施設に児童を預けることができる事業です。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
2.認定及び利用の申し込みをする
希望園と希望の利用形態が決まったら、認定申請及び利用申し込みを行っていただきます。
それぞれの認定区分やご希望の入所月によって受付場所や受付期間等が異なります。
1号認定(教育標準時間認定)の申し込み
受付場所
ご希望の各施設
受付期間
令和7年度入所分
令和6年11月22日(金曜日)より随時
なお、各年度ともに入所を希望する月によって締切日が異なりますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。
必要書類
全ての方に共通の書類
・施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書
(ピンク色の申請書)
必要に応じて提出する書類
・園に提出を求められた書類
2・3号認定(保育認定)の申し込み
受付場所
宇佐市役所本庁 子育て支援課または安心院・院内各支所 市民サービス課
*宇佐市内に住民票のある児童に限る
受付期間
令和7年度入所分
| 募集 | 受付開始日 | 締切日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 一次募集 | 令和6年11月25日(月曜日) | 令和6年12月20日(金曜日) | 終了 |
| 二次募集 | 令和7年2月3日(月曜日) | 令和7年2月7日(金曜日) | 終了 |
| 4月1日入所分 | 令和7年2月17日(月曜日) | 令和7年3月10日(月曜日) | 終了 |
| 5月1日入所分 | 令和7年3月11日(火曜日) | 令和7年4月15日(火曜日) |
終了 |
| 6月1日入所分 | 令和7年4月16日(水曜日) | 令和7年5月15日(木曜日) | 終了 |
| 7月1日入所分 | 令和7年5月16日(金曜日) | 令和6年6月16日(月曜日) | 終了 |
| 8月1日入所分 | 令和7年6月17日(火曜日) | 令和7年7月15日(火曜日) | 終了 |
| 9月1日入所分 | 令和7年7月16日(水曜日) | 令和7年8月15日(金曜日) | 終了 |
| 10月1日入所分 | 令和7年8月18日(月曜日) | 令和7年9月16日(火曜日) | 終了 |
| 11月1日入所分 | 令和7年9月17日(水曜日) |
令和7年10月15日(水曜日) |
終了 |
| 12月1日入所分 | 令和7年10月16日(木曜日) | 令和7年11月17日(月曜日) | 終了 |
| 1月1日入所分 | 令和7年11月18日(火曜日) | 令和7年12月15日(月曜日) | 受付中 |
| 2月1日入所分 | 令和7年12月16日(火曜日) | 令和8年1月15日(木曜日) | 未 |
| 3月1日入所分 | 令和8年1月16日(金曜日) |
令和8年2月16日(月曜日) |
未 |
各施設の募集数は一次募集開始時に更新されます
原則として、申し込みは入所月の直前(一次募集、二次募集4月1日入所分では4月1日入所もしくは5月1日入所)の受付となります。
ただし、令和6年度内で5月以降に保育を必要とする事由が明確に決まっている方は、一次募集時点から事前に申し込みができます(締切日は同じです)。また、該当する方については、入所する児童の出産前に申し込みができる場合があります。事由に応じた必要書類の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
令和7年度1月以降の保育施設入所募集数のお知らせ(12月募集)
必要書類
全ての方に共通の書類
・施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書
(黄色の申請書)
・保育施設利用に関する調査票(表面)兼保育施設利用・保育認定に関する確認書(裏面)
・保育を必要とする事由に応じて提出する証明書
(下表「保育を必要とする事由に応じて提出する証明書の一覧」を参照)
| 事由 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 就労 | 就労証明書 | シフト制など不規則勤務で、証明書では表記しきれない場合は、シフト表など勤務形態が確認できるものが必要 |
| 妊娠・出産 | 母子健康手帳のコピー | 表紙・出産予定日がわかるページ |
| 疾病・障がい | 病気等証明書(病気・障がい用)*または障害者手帳等のコピー | 障害者手帳等で保育の必要性が確認できない場合は病気等証明書(病気・障がい用)も必要 |
|
介護・看護 |
病気等証明書(介護・看護用)* | |
| 災害復旧 | 罹災証明 | |
| 求職活動 | 求職活動申立書 | |
| 就学 | 在学証明書 日数及び時間が確認できるカリキュラム |
|
| 育児休業 | 就労証明書 | 休業期間の証明のあるものが必要 |
| その他 | 状況に応じた書類 |
!注意!
・*マークがついている証明書は宇佐市独自の様式です。
また、就労証明書は国の標準様式です。
・就労証明書は事業主の方に証明(記入)いただく書類です。
雇用形態が「自営業主」「自営業専従者」「家族従業者」の場合は、就労状況を証明する書類(確定申告書、開業届の写しなど)も必要です。
また、期限付き雇用の方は期限の更新ごとに就労証明書の提出が必要です。
・病気証明書は医師に証明(記入)いただく書類です。
第1子で3歳未満の児童
・多子確認書
第2子で3歳未満の児童
・宇佐市にこにこ保育支援事業助成申請書
(保育料減免のための申請書 詳細は下記リンク先をご覧ください。)
状況に応じて提出する書類
・同居の扶養義務者(20歳以上60歳未満の児童の祖父母もしくはきょうだい)の保育を必要とする書類
3.入所の決定(内定)を受ける
認定区分によって入所決定(内定)までの流れが異なります。
1号認定の入所決定(内定)
結果連絡について
申し込みをした施設より結果連絡があります。詳細は施設にお問い合わせください。
入所が決定したら
施設より入園の準備等についてのご連絡があります。
2・3号認定の入所決定(内定)
結果連絡について
各受付期間の終了後に、利用調整を行います。調整基準に基づき、保育の必要性の高い児童から順に入所を決定(内定)します。
申し込み状況によっては希望の施設に入所できない場合がありますので、予めご了承ください。
一次募集で申し込みをした方には1月末に、二次募集で申し込みをした方には2月下旬に、それぞれ結果通知を発送します。
二次募集以降に申し込みをした方は、直近の審査後(毎月20日前後)に電話等で結果連絡をします。
入所が決定したら
4月入所の方
3月上旬から中旬に施設より入園の準備等についての連絡があります。
施設の新年度の準備が整っていない場合もございますので、園からの連絡があるまでのお問い合わせについては子育て支援課までお願いいたします。
4月の入所時に施設を経由して支給認定証と入所決定通知をお渡しします。
5月以降入所の方
入所月の前月下旬ごろに施設または子育て支援課より電話等で確認の連絡をします。
入所時に施設を経由して支給認定証と入所決定通知をお渡しします。
4.利用を始める
ならし保育について
児童の体調に配慮しながら集団生活にスムーズに慣れさせるため、おおむね2週間程度(児童の状況に応じて差があります)の間、時間を短縮して通園する「ならし保育」の期間を設けています。
ならし保育は入所してから開始されます。
延長保育の利用について
保護者の勤務時間等の都合で、通常の保育時間後も保育を必要とする児童に向けて延長保育を実施している施設があります。
利用できるのは延長保育を実施している施設に入所している児童に限られます。
利用には別途延長保育の利用申請が必要です。
保育料等について
施設を利用する際に、所得や児童の年齢に応じて算定される保育料や、園で生じる教材費、給食費などの雑費が発生します。
金額や制度等については下記リンク先をご覧ください。
認定及び施設利用にあたっての注意事項
内容の変更について
世帯状況や保育を必要とする事由など、申請時点と状況が変わる場合は届け出が必要です。状況に応じて手続きの内容が変わりますので、詳細は利用施設または子育て支援課までお問い合わせください。
休園・退所について
施設をお休みする場合、必ず事前に利用施設へ連絡をしてください。
また、以下に該当する場合に退所していただくことがありますので、予めご了承ください。
・無断欠席や1カ月以上の長期欠席等出席日数が著しく少ない場合
・児童の心身状態により医師によって集団生活になじまないと判断された場合
・届け出の内容に虚偽の事項が判明した場合
・入所理由が消滅した場合
児童が宇佐市外に転出する際は退所届が必要です。引き続き利用施設を継続する場合は、転出先の自治体で認定申請と入所申し込みが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 保育支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8144
ファックス:0978-27-8227
メールフォームによるお問い合わせ
- 宇佐市子育て支援サイトのページに関する評価
-
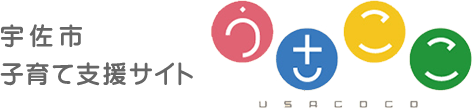
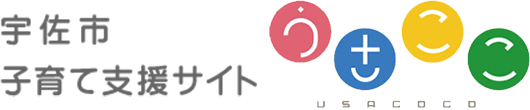
更新日:2025年10月16日