子どもの定期予防接種について
予防接種は、感染症が流行するのを防ぎ、病気にかからないように、あるいは、かかっても重くならないようにするためのものです。
お母さんが妊娠中に、お母さんから赤ちゃんへ免疫が移行します。この、お母さん由来の免疫は、成長とともにほとんどが自然に失われてしまいます。また、子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。
そのため、子ども自身で免疫をつくって病気を予防する必要があり、その助けとなるのが予防接種です。
子どもの体質はそれぞれ違うため、程度に差がありますが、副反応が生じる場合があります。
事前に、市が配布しています「予防接種と子どもの健康」をよく読み、予防接種について正しく理解したうえで、お子さんの体調の良い時を選んで予防接種を受けることが大切です。
接種方法
- 定期予防接種は定められた接種期間内であれば、無料で接種できます。
- 宇佐市では、医療機関での個別接種となります。
接種を希望される場合、事前に接種医療機関に電話予約が必要です(医療機関によって接種できる予防接種が異なります) - 予防接種を受ける際は、母子健康手帳と予診票をご持参のうえ、保護者同伴で受けてください。
ただし、13~15歳の方については、あらかじめ接種することの保護者の同意を予診票の裏面に記載されている同意書にて確認できる場合は、保護者の同伴は必要ありません。
保護者以外の方が接種に同伴する場合は、予診票の裏面に記載されている保護者の委任状への記入が必要になります。
その他の予防接種情報
- 長期にわたる疾患等のために定期接種を受けられなかった方については、定められた接種期間を超えて接種できる場合があります。
- 県外の医療機関で接種を希望する場合は、窓口で接種料金を一旦お支払いいただきますが、後日市に申請していただくことで、市が定める接種費用を上限として保護者あてに接種費用をお返しできます。
(注意)ただし、1、2ともに予防接種を行う前に市への申請が必要になります(事前に申請がない場合は、接種料金は有料になります)。必ず事前にお問い合わせください。
予防接種法に基づく予防接種
ロタウイルスワクチン
令和2年10月1日からロタウイルスワクチン感染症の予防接種が定期接種になりました。
ロタウイルスワクチンには2種類あり、同様の効果があります。
2つのワクチンは接種回数が異なります。最初に受けたワクチンと同じ種類を接種していきましょう。(市内医機関は主に5価ロタウイルスワクチンを使用しています)
(注意)出生15週0日以降の初回接種については安全性が確立していません。出生14週6日までに、1回目の接種を受けましょう。
5価ロタウイルスワクチン(ロタテック)
・接種可能な期間:出生6週0日後から32週0日までの間
| 接種回数 |
接種間隔 |
|---|---|
| 3回 | 生後2月に至った日から生後14週6日後までの間に接種開始 27日以上の間隔をおいて3回接種 |
1価ロタウイルスワクチン(ロタリックス)
・接種可能な期間:出生6週0日後から24週0日までの間
| 接種回数 | 接種間隔 |
|---|---|
| 2回 | 生後2月に至った日から生後14週6日後までの間に接種開始 27日以上の間隔をおいて2回接種 |
接種後1~2週間は「腸重積症」に注意しましょう!
腸重積症は、腸の一部が隣接する腸管にはまり込み、腸の血流が悪くなることで腸の組織に障害を起こすことがあるため、速やかな治療が必要となります。ワクチン接種から1~2週間くらいまでの間には、腸重積症の発症の可能性が通常より高まると報告もあります。
腸重積症はロタウイルスワクチンの接種にかかわらず、乳幼児がり患することのある疾患で、まれな病気ではありません。
接種後に以下の症状が一つでも見られた場合は速やかに医療機関に相談、受診しましょう
- 「突然はげしく泣く」
- 「機嫌が良かったり不機嫌になったりを繰り返す」
- 「嘔吐する」
- 「血便がでる」
- 「ぐったりして顔色が悪い」
リンク
厚生労働省のホームページにて、予防できる病気や、ワクチンについての説明を見ることができます。
B型肝炎ワクチン
・接種可能な期間:1歳の誕生日の前日までの間
| 接種回数 | 接種間隔 |
| 初回(2回) |
《標準的な接種期間》生後2月から生後9月に至るまでの間 27日以上の間隔をあけて2回接種 |
| 追加(1回) | 第1回目の注射から139日以上あけて1回接種 |
(注意)母子感染予防として出生後にB型肝炎ワクチンを接種したことがある方や任意接種ですでに3回接種した方は対象外です。
リンク
厚生労働省のホームページにて、予防できる病気や、ワクチンについての説明を見ることができます。
子どもの肺炎球菌ワクチン
・接種可能な期間:生後2か月から5歳の誕生日の前日までの間
接種開始期間(月齢)により以下のとおり接種回数が異なります
| 接種回数 | 接種間隔 |
|---|---|
| 初回(3回) |
≪標準的な接種期間≫1歳までに27日以上の間隔をおいて3回接種 2歳の誕生日の前日までの間に27日以上の間隔をおいて3回接種 1歳以降に2回目の接種を受ける場合は、3回目は接種しません。 2歳以降は初回接種の続きを受けることはできません。 |
| 追加(1回) | ≪標準的な接種期間≫初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて1歳から1歳3か月の間に1回接種
初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて1歳の誕生日の前日以降に1回接種 |
| 接種回数 | 接種間隔 |
|---|---|
| 初回(2回) | ≪標準的な接種期間≫1歳までに27日以上の間隔をおいて2回接種
2歳の誕生日の前日までの間に27日以上の間隔をおいて2回接種 2歳以降は初回接種の続きを受けることはできません。 |
| 追加 | 初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて1歳の誕生日の前日以降に1回接種 |
| 接種回数 | 接種間隔 |
| 初回(2回) | 60日以上の間隔をおいて、2回接種 |
- 2歳以降に接種開始した場合は1回接種のみ
リンク
厚生労働省のホームページにて、予防できる病気や、ワクチンについての説明を見ることができます。
5種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・Hib)
令和6年4月1日から5種混合ワクチンが定期接種になりました。
5種混合ワクチンは今までの4種混合ワクチンにHibワクチンが加わったものです。
4種混合ワクチン・Hibワクチンを接種している方は、引き続き必要回数を接種してください。新たに5種混合ワクチンを接種する必要はありません。
・接種可能な期間:生後2か月~生後90か月(7歳5か月)に至るまでの間
| 接種回数 | 接種間隔 |
|---|---|
|
1期初回(3回) |
≪標準的な接種期間≫生後2か月から7か月に至るまでに開始 20日以上(標準的には20日から56日)の間隔をおいて3回接種 |
| 1期追加(1回) |
≪標準的な接種期間≫1期初回3回終了後6か月から18か月までの間に1回接種 1期初回接種3回終了後、6か月以上の間隔をおいて1回接種 |
リンク
厚生労働省のホームページにて、予防できる病気や、ワクチンについての説明を見ることができます。
BCGワクチン
・接種可能な期間:1歳になる前日までの間
≪標準的な接種≫生後5か月から生後8か月に1回接種
リンク
厚生労働省のホームページにて、予防できる病気や、ワクチンについての説明を見ることができます。
麻しん(はしか)・風しん混合 ワクチン:MRワクチン
MR第1期の接種可能な期間:1歳~2歳の誕生日の前日までの間に1回接種
MR第2期の接種可能な期間:小学校入学前の4月1日~翌年3月31日までの1年間に1回接種(5歳以上7歳未満の方)
※接種可能な期間が短いので、なるべく早く接種しましょう
リンク
厚生労働省のホームページにて、予防できる病気や、ワクチンについての説明を見ることができます。
水痘ワクチン(みずぼうそう)
・接種可能な期間:1歳から2歳11か月までの間
| 接種回数 | 接種間隔 |
|---|---|
| 2回 |
《標準的な接種期間》1歳から1歳3か月までに接種開始し、1回目の接種終了後、6か月から1年の間隔を置いて1回接種 3か月以上の間隔をおいて2回接種 |
リンク
厚生労働省のホームページにて、予防できる病気や、ワクチンについての説明を見ることができます。
日本脳炎ワクチン
・第1期の接種可能な期間:生後6か月から生後90か月に至るまでの間
・第2期の接種可能な期間:9歳から13歳の誕生日の前日までの間
| 接種回数 | 接種間隔 |
|---|---|
| 第1期初回(2回) |
≪標準的な接種期間≫3歳から4歳になるまでの間に6日から28日までの間隔をおいて2回接種 6日以上の間隔をおいて2回接種 |
| 第1期追加(1回) |
≪標準的な接種期間≫4歳から5歳になるまでの間に1期初回接種後概ね1年の間隔をおいて1回接種 1期初回接種後6か月以上の間隔をおいて1回接種 |
| 第2期(1回) |
≪標準的な接種期間≫9歳から10歳になるまでの間に1回接種 9歳から13歳の誕生日の前日までに1回接種 |
リンク
厚生労働省のホームページにて、予防できる病気や、ワクチンについての説明を見ることができます。
2種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風)
・接種可能な期間:11歳から12歳の誕生日の前日までの間に1回接種
≪標準的な接種期間≫11歳~12歳になるまでの間に1回接種
リンク
厚生労働省のホームページにて、予防できる病気や、ワクチンについての説明を見ることができます。
ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)
HPVワクチンは、平成25年6月から接種後に生じうる多様な症状等について十分に情報提供できない状況にあったことから、個別に接種をお勧めする取組を一時的に差し控えていました。令和3年11月の専門家の会議で、安全性について特段の懸念が認められないことが改めて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、個別に接種をお勧めする取組を再開することになりました。
・接種可能な期間:12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間(女性のみ)
≪標準的な接種期間≫中学1年生相当で接種開始
原則、同一のワクチンを使用して接種を完了してください。
ただし、2価ワクチン又は4価ワクチンの接種歴のある方が9価ワクチン接種を検討されている場合は、接種を実施する医療機関の医師と被接種者とで十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択してください。(2価ワクチンと4価ワクチンの併用はできません。)
※ワクチンの種類により、接種回数、接種間隔が異なります
| 接種時期 | 接種間隔 | |
| 15歳以降に接種開始(3回) |
2回目 |
≪標準的な接種期間≫1回目の接種から2か月後 1回目の接種から1月以上の間隔をおいて接種 |
| 3回目 |
≪標準的な接種期間≫1回目の接種から6か月後 2回目の接種から3月以上の間隔をおいて接種 |
|
| 15歳未満に接種開始(2回) | 2回目 |
≪標準的な接種期間≫1回目の接種から6か月後 1回目の接種から少なくとも5月以上の間隔をおいて接種 ※5月未満で2回目を接種した場合は3回の接種のスケジュールに沿って3回目の接種を行う |
| 接種回数 | 接種間隔 | |
| 3回 | 2回目 |
≪標準的な接種期間≫1回目の接種から2か月後 1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて接種 |
| 3回目 |
≪標準的な接種期間≫1回目の接種から6か月後 2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて接種 |
|
| 接種回数 |
接種間隔 |
|
|---|---|---|
| 3回 | 2回目 |
≪標準的な接種期間≫1回目の接種から1月後に接種 1回目の接種から1月以上の間隔をおいて接種 |
| 3回目 |
≪標準的な接種期間≫1回目の接種から6月後に接種 1回目の接種から5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて接種 |
|
リンク
厚生労働省のホームページにて、予防できる病気や、ワクチンについての説明を見ることができます。
HPVワクチンに関する相談先一覧
HPVワクチンに関してのご相談は以下をご参照ください。
接種後に、健康に異常があるとき
まずは、接種を受けた医師・かかりつけの医師にご相談ください。
各都道府県において、「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」を選定しています。
協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。
不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき
各都道府県において、衛生部局と教育部局の1箇所ずつ「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口」を設置しています。
HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談
「感染症・予防接種相談窓口」では、HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。
電話番号:0120-995-956
受付時間:平日9時から17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
(注意)行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
(注意)本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。
予防接種による健康被害についての補償(救済)に関する相談
お住まいの市区町村の予防接種担当部門にご相談ください。
HPVワクチンを含むワクチン全体の健康被害救済制度については、「予防接種健康被害救済制度」のページをご覧ください。
予防接種を希望する場合
接種を希望する方については、定期接種としての接種が可能であり、万が一健康被害が生じた場合には予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
今後も接種を希望する方は、従来どおり予防接種の効果や目的、重篤な副反応などについて理解をしていただき、併せて「厚生労働省ホームページ」をお読みいただき保護者の同意のもとで接種をお願いします。
一般の方向け情報提供資材
小学校6年から高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版) (PDFファイル: 3.2MB)
小学校6年から高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版) (PDFファイル: 7.3MB)
HPVワクチンの接種を受けた方へ
HPVワクチンの接種を受けた後は、体調に変化がないか十分に注意してください。
詳しくは、「HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ」をご覧ください。
HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ (PDFファイル: 1.3MB)
4種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)
令和6年度から、5種混合ワクチンが定期接種になりましたが、4種混合ワクチン・Hibワクチンを接種している方は、引き続き必要回数を接種してください。新たに5種混合ワクチンを接種する必要はありません。
・接種可能な期間:生後2か月~生後90か月に至るまでの間
| 接種回数 | 接種間隔 |
|---|---|
| 1期初回(3回) |
≪標準的な接種期間≫生後2か月から12か月に20日から56日までの間隔をおいて3回接種 20日以上の間隔をおいて3回接種 |
| 1期追加(1回) |
≪標準的な接種期間≫1期初回3回終了後12か月から18か月までの間隔をおいて1回接種 1期初回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて1回接種 |
リンク
5種混合ワクチンのページで、4種混合ワクチンについての説明を見ることができます。
ヒブワクチン
5種混合ワクチンを1回目から接種されている方は、ヒブワクチンを接種する必要はありません。
・接種可能な期間:生後2か月~5歳の誕生日の前日までの間
接種開始期間(月齢)により以下のとおり接種回数が異なります
| 接種回数 | 接種間隔 |
|---|---|
|
初回(3回) |
≪標準的な接種期間≫27日以上56日までの間隔をおいて3回接種 27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて3回接種 初回の3回は1歳の誕生日の前日までに終える必要があります。 |
| 追加(1回) | ≪標準的な接種期間≫初回接種終了後、7ヵ月以上13ヵ月までの間隔をおいて1回接種 初回接種終了後、7ヵ月以上の間隔をおいて1回接種 3回の初回接種を完了せずに1歳以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回接種 |
| 接種回数 | 接種間隔 |
|---|---|
| 初回(2回) | ≪標準的な接種期間≫27日以上56日までの間隔をおいて2回接種 27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて2回接種 初回の2回は1歳の誕生日の前日までに終える必要があります。 |
| 追加(1回) | ≪標準的な接種期間≫初回接種終了後、7ヵ月以上13ヵ月までの間隔をおいて1回接種 初回接種終了後、7ヵ月以上の間隔をおいて1回接種 2回の初回接種を完了せずに1歳以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回接種 |
- 1歳以降に接種開始した場合は1回接種のみ
リンク
5種混合ワクチンのページで、ヒブワクチンについての説明を見ることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 母子保健係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8145
ファックス:0978-27-8227
メールフォームによるお問い合わせ
- 宇佐市子育て支援サイトのページに関する評価
-
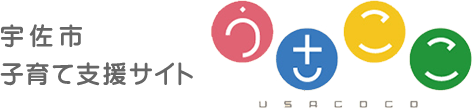
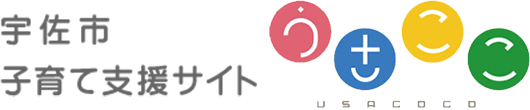
更新日:2025年06月01日